
けんけんです!
文学に学ぶシリーズ、少し古い文学作品の中から、教訓の多いものを選んでご紹介し、現代に当てはめて考察してみようという企画です。今回、2回目です。
◆この記事を読んで得られるメリット
①普段、あまり目にしない文学作品に触れられる
②登場人物の言動から、学ぶべきものが理解できる
③現代に当てはめて、今からあなたがすべき行動がわかる
◆結論
精神的にも、物質的にも、自分軸をしっかり持ったブレない生き方をする
スポンサーリンク
1.はじめに
コロナが日本でも騒がれ始めて、2年になろうとしています。
最近はワクチン接種が進み、やや落ち着いてきた感じもしますが、重症の方や後遺症に苦しむ方もいらっしゃいます。
現在、療養中の方々の1日も早いご回復をお祈りします。
また、僕は、国民代表でもなんでもないですが、医療関係者の方々の日々のご尽力に、尊敬と感謝の気持ちを表したいです。

コロナは、いつか終息するでしょう。でも、世の中はコロナ前の状態には、もう戻らないでしょう。
コロナ後の新しい現実があるだけです。新しい現実の世界で生きていく必要があります。
2.「山月記」の内容紹介
この内容は、別記事 「自己肯定感を高める 文学に学ぶシリーズ 中島 敦著「山月記」より」の『1.「山月記」の内容紹介』と同じ内容ですので、すでにご存じの方は読み飛ばしてください。
「山月記」は中国 唐の時代を舞台にした話です。
文庫本で10ページ弱の短い話ですが、考えさせられることの多い物語です。

とても印象に残っています
このブログを書くにあたり
文庫本で読み直しました
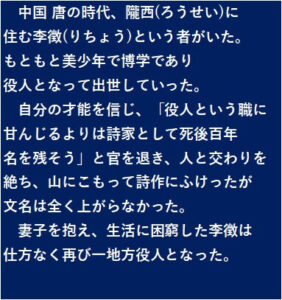

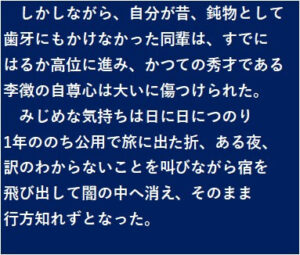

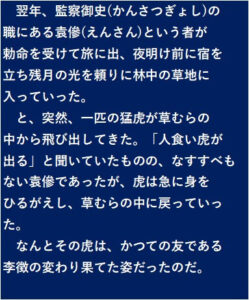

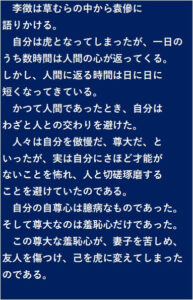

「尊大な羞恥心」の
2つの言葉が、この物語の
キーワードになっています
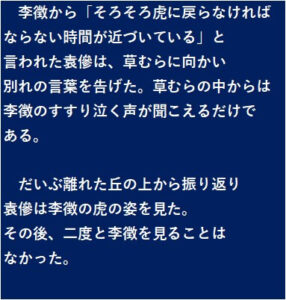
何か悲しいお話ですね


でも、この物語の中には
色々な教訓があります
スポンサーリンク
3.「ひとりで生きていく」 自立と孤立のちがい
虎は、アジアの文化において力や威厳の象徴として、古来から親しまれてきました。

どんなものがあるか
わかりますか?
一頭で生活している
イメージがあります

虎は、母親と子供は一緒に暮らしますが、それ以外は単独で生活することが多いと考えられています。
仲間と離れてひとりでいた李徴の行動も、そうした虎の生態とよく合っていたと言えるでしょう。李徴が、猿など群れを作って暮らす動物という想定は、この物語の主題とは外れてしまいます。(ただし、雄猿は、普段は群れから離れて単独行動し、交尾期だけ群れに交わるらしいですが)

人の生き方について、「人はひとりで生きていくもの」という考え方と、「人はひとりでは生きていけない」という考え方があります。 「ひとり」の意味が違います。
「ひとり」で生きるの「ひとり」とは、「自立」と「孤立」の2種類があります。
自立:自力でものごとをやっていくこと
↑「人はひとりで生きていくもの」に近い考え方
孤立:ひとりだけぽつんと存在すること
↑「人はひとりではいきていけない」に近い考え方

多かったようですが
「自立」と「孤立」
どちらのタイプだったでしょう?
「孤立」だった気がします

「自立」というのは、精神的にも物質的にも周りから独立して、周りの状況や周りからの評価に左右されることなく、自分を貫くことです。「ブレない」や「自分軸がしっかりしている」とも言い換えられます。
李徴の場合は「実は自分にさほど才能がないことを怖れ、人と切磋琢磨することを避けていた」と言っていますよね。傲慢で尊大なようでも、その内心は、自分と他人を比べ自分の才能のなさを怖れていたわけです。 精神的に独立できているとは言えず、「孤立」していただけです。
わあ李徴さん、すごい!
とか、周りから持ち上げ
られたりしたら、もう少し
周りの人とも打ち解けられ
たんでしょうか?


それは正しいコミュニケーション
ではありませんね
メンヘラちゃん
だったんですか?

◆メンヘラとは
もともとネット上のスラングであり、ネットの掲示板等にメンタルヘルスに関する書き込みをよくする人のことを意味していました。
そのような人たちは「メンヘラー」と呼ばれ、メンタルヘルスに問題を抱えている人のことを意味しました。
「メンヘラー」は「メンヘラ」に変わり、最近は、人にかまってもらいたい「かまってちゃん」の意味で使われることも多くなりました。


中島 敦氏は、李徴をそういう
設定で書いてはいなかったかも
しれませんが
現代に置き換えると
李徴=実はメンヘラ、という
説も否定はできませんね
李徴がメンヘラかどうかは一旦脇に置くとして、李徴も「孤立」ではなく「自立」し、しっかり自分軸をもったブレない生き方ができていれば、虎にはならずに済んだと考えて間違いないでしょう。
4.現代に置き換えて考えてみる
李徴の生き様を考察し、私たちに必要なことを考えると、次のことが言えます。
精神的にも、物質的にも、自分軸をしっかり持ったブレない生き方をする
コロナ禍の現代、私たちは不安だらけです。
◆日常生活の不安
①コロナに感染したらどうしよう
②自粛生活はいつまで続くんだろう
③勤務先や学校で普段通りの生活ができない
④外に出かけるのが怖い

◆金銭的な不安
①お客様が減ること等による減収、廃業
◆医療対応に関する不安
①医療機関は満杯、自分が感染したら十分な処置が受けられるのか
②ワクチン接種はどれだけ効果があるか、副反応はどうか
これら以外にも、住んでいる地域や個人の個別の事情によるものも含めて、様々な不安があります。

先ほど、李徴の話の中で、李徴も「孤立」ではなく「自立」し、しっかり自分軸をもったブレない生き方ができていれば良かったと書きました。
「自立」とは、精神的なものと、お金を含む物質的なものについて独立することです。
◆精神的な「自立」
①自分と他人を比べない
②相手の立場や気持ちを考え、依存しない
③他人からの評価を気にしない
◆物質的な「自立」
①組織や人に頼らず、一人でも生きていけるよう複数の収入源を得る(例えば副業や起業等)
②手に職をつける、資格を取るなど、スキルアップをする
③日常生活、事業での支出(特に固定費)を極力削減する
他人、組織に頼らずに生きていくすべを身につけ、自分軸を持ったブレない生き方を目指しましょう。
5.まとめ
◆私たちが目指す生き方
精神的にも、物質的にも、自分軸をしっかり持ったブレない生き方をする
◆そのために、すべきこと
◆精神的な「自立」
①自分と他人を比べない
②相手の立場や気持ちを考え、依存しない
③他人からの評価を気にしない
◆物質的な「自立」
①組織や人に頼らず、一人でも生きていけるよう複数の収入源を得る(例えば副業や起業等)
②手に職をつける、資格を取るなど、スキルアップをする
③日常生活、事業での支出(特に固定費)を極力削減する
◇◆◇ ◆◇◆ ◇◆◇ ◆◇◆ ◇◆◇
編集後記
みなさん、今回の内容、いかがでしたか?
「山月記」の著者、中島 敦氏は大正から昭和初期にかけて作品を発表した作家です。
後の世に、物語の主人公が「メンヘラ」呼ばわりされるとは夢にも思っていなかったでしょう。
関連記事として以下があります。合わせてご覧いただければうれしいです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
これからも、みなさんのお役に立つ情報を発信していきます。

思った方
下のボタンをクリック
してください!
日本ブログ村ランキング
に参加しています
スポンサーリンク


